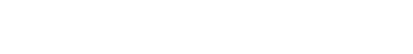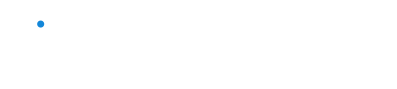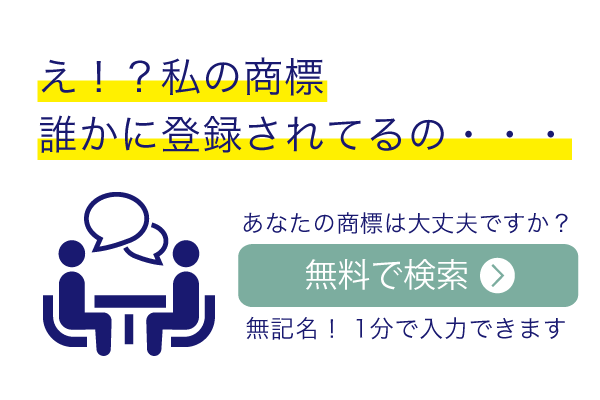マイケル・ジョーダン氏、商標権問題で中国企業を提訴
米国のプロバスケットボールNBAで「神様」と呼ばれた往年の名選手マイケル・ジョーダン氏が、自分の名前の中国語表記「喬丹(チアオタン)」を無断で商標登録されたとして、中国のスポーツ用品メーカーを中国の裁判所に提訴していたことが分かった。(中略)
精神的に受けた損失に対して1千万元(約1億3千万円)以上の賠償を求めているという。
2012/2/24 【朝日新聞】
前編の続き「中国の商標登録トラブル」
—今度はジョーダンにエルメスも
こんにちは。iRify特許事務所・新米編集長の浅見です。
さあ、そろそろ花粉の季節到来ですね。先日、地下鉄でずっとクシャミを繰り返している人を目にしましたが、あれは辛そうです。今まで花粉症に無縁だった人も、自分は大丈夫だから、などと泰然と構えていてはいけません。
「魔女の一撃」とも称されるギックリ腰のように、花粉症発症の瞬間は突如として訪れるものですから、どうかご用心。
さて前回は、アップルの商標やブランド力に乗っかった中国のフリーライド(ただ乗り)商品のあれこれをご紹介してきました。
今回はその続き。アメリカのバスケ界の元スター「マイケル・ジョーダン」や、フランスの有名ブランド「エルメス」が、中国で巻き込まれた商標登録トラブルについてのお話をお届けしたいと思います。
そこから、中国の商標登録事情を、少しばかり眺めていければと思います。
個人・法人問わず、有名だったら即商標登録?

マイケル・ジョーダンさんの中国名が商標登録
アップルは天下の著名ブランドですが、中国では、有名な一個人が商標登録トラブルに巻き込まれることも珍しくはありません。今、大きく報道されているのは、NBAで活躍した往年の大選手・マイケル・ジョーダンさんの商標登録トラブルの一件。今年の2月にジョーダンさんが、自分の名前を無許可で商標登録されたとして、中国・福建省のスポーツ用品メーカー・「喬丹体育」を提訴したという件です。
登録された商標は「喬丹(チアオタン)」。
これ、「ジョーダン」の中国語訳なんですって。
喬丹体育では、ジョーダンさんのシルエットを想起させるロゴが使われていたり、現役時代の背番号「23」を施したユニフォームが売られていたりと、どうも以前から問題視されていたようです。確かに、そのロゴはシカゴ・ブルズ時代のジョーダンさんの勇姿を思わせなくもないような…。
一方で、訴えられた喬丹体育側はというと、「“喬丹”は一般的な外国人の姓で、ジョーダンさんとは無関係」と説明しています。さらに「“喬丹”の名前は2000年の創業当時から使用しており、中国本土では商標も正式に取得している」とのこと。
結果、裁判所も「“喬丹”は一般名」と判断し、ジョーダンさんの訴えを退けています。
フランス・エルメスも?—商標権争いで中国の紳士服メーカーに敗れる

またも有名ブランドの話題に立ち戻りますが、あのフランスの「エルメス」も、目下、中国の商標登録トラブルに悩まされています。
エルメス・インターナショナルの中国語表記は「愛馬仕(アイマーシー)」。対して、中国には「愛瑪仕」というエルメスの中国名によく似た商標を登録している企業があるのです。広東省にある紳士服メーカー・「順徳達豊制衣」です。ちなみに、「愛馬仕」と「愛瑪仕」—この2つの発音は同じだといいます。商標的にとてもグレーな感じがします。
しかし今回、中国の裁判所は、この商標登録の取り消しを求めていたエルメスの訴えを退けています。エルメスは1977年の時点で、中国での商標登録を済ませていて、中国でも有名なブランドとして定着していました。しかし、ローマ字でのみの登録だったこともあってか、今回、敗訴となってしまいました。
中国の商標登録トラブル—どうする、その対策?
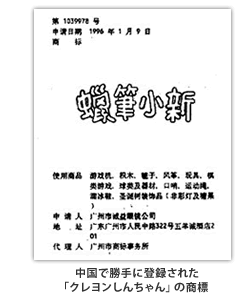
海外の有名なブランドや一個人、地名などが勝手に商標登録されるという中国での商標トラブルの話題は、アップルの件もあってか最近とくに耳目を集めているように感じます。
例を挙げれば、お米では新潟県産「コシヒカリ」や宮城県産「ひとめぼれ」、アニメでは「クレヨンしんちゃん」。それに、岐阜県の「美濃焼」や石川県の「九谷焼」などの陶磁器ブランド。さらに、「青森」「京都」「長野」「名古屋」「横浜」といった地名に関するものなど、枚挙に暇はありません。日本としては、これは困ります。
中国の「冒認出願」—どうすればいいの?教えて加藤さん!
—さあ、困ったところで、わがiRify特許事務所・所長弁理士の加藤さんにお話を聞いてみましょう。加藤さん、こういった中国での商標トラブル、どうしたらいいんでしょうか?やはり、あれですか?法に訴えるというやつですか?
「はは、いきなり穏やかじゃないね。もちろん、こういった冒認出願と思われる商標に対しては、異議を申し立てるなり、無効審判に持ち込むなり、色々と手段はあるにはあるよ」
—? ボウニン、なんですか?
「ああ、ごめんごめん。冒認出願ね。『抜け駆け登録』って言えばわかりやすいかな?ぜんぜん関係のない第三者が、本来の権利者の知らぬうちに商標出願することを、そう呼んでいるんだ。まあ、知財関係の業界用語だね」
—なるほど、では、そのボウニンに対しては、ビシッと訴え出てやればいいんですね?
「いやいや、一概にはそうとも言えないよ。異議申し立てや無効審判だってタダじゃないし、もし訴訟にでも発展してしまったら、それはもう弁護士マターだよ。お金も時間も労力もかかってくる」
—弁護士マター、ですか?
「うん。もう、弁護士さんの領分ってこと。そうして、お金をかけて弁護士さんにお願いしたって、100%勝てる保証なんていうのはないんだから。訴訟っていうのは、コストや勝つ見込みをしっかりと見越した上で選ぶべき選択肢だと思うね」
—じゃあ、ボウニン出願されても黙って見過ごすということですか?
「それも戦略のひとつではあるね。あるいは、その商標権者から商標権を譲り受けるという手もある」
—え? 不正に出願された商標を、わざわざお金を出して買い取るってことですか? なんだか釈然としないなあ。
「でも、訴訟のリスクと天秤にかけたときに、どちらが得か、どちらが被害を最小限に抑えられるかを冷静に考えるのは、戦略として大切なことなんじゃないかな」
中国の商標登録の実態— 商標ブローカー的な側面もあるにはあるけど…
—う〜ん、なるほど。でもですね、そもそもの話、そんなボウニン出願が登録されちゃうこと自体、ゆゆしきことだと、ぼくは思うんですけど…。中国の特許庁の審査基準って、一体どうなってるんですか?
「中国の商標出願・審査に関しては、『中国商標局』という商標専門の機関が受け持っているんだ。異議の申し立てもここにする」

—あ、そうなんですか。特許庁ってのはないんですね、メモメモ。
「たしかに中国は、海外の有名ブランドや地名に対する保護が不十分だというきらいはあるね。一応、海外の著名商標や地名を保護する規定もあるんだけれど、『中国国内における著名性』を論ずるときには、どうしても不明確さが残ってしまう」
—そうですよ。エルメス商標の件も、結局、エルメス(愛馬仕)ブランドが「中国では一般に広く知られてはいない」と判断されて、訴えが却下されたっていうじゃありませんか。
「そうだね。有名・無名の判断は主観に陥りやすいからね。エルメスほどのブランドでも著名性が否定されてしまったんだから、他は推して知るべし。日本で有名だとしても、中国で知られていないって判断されたら、残念ながら冒認出願はそのまま登録されてしまうんだ」
—ボウニン出願は防げないし、訴訟でも勝てるかわからない。それじゃ、打つ手はないじゃないですか。
「後手後手に回ったら、たしかにそうかもしれない。でも、事前の予防策をしっかりしておけば、ある程度のリスクヘッジはできるものだよ」
—そうなんですか! ぜひ、それを教えてください。
「うん。じゃあ、今から言う3つのポイントをよく覚えておくようにね。
(1) 文字だけでなく、図形と合わせるなど、“識別力”を高めたロゴマーク商標で出願する。
(2) 中国文化圏(香港・マカオ・台湾)に商標出願する際は、中国大陸での商標登録出願も忘れない。
(3) 今後、事業展開する予定の指定商品・サービスだけでなく、もっと広い範囲で出願・登録する(冒認出願者が手を出しやすい「被服」「日用品」などの分野はとくに)。
…以上、こんなところかな」
—なるほど、ようするに、こっちが先に広い範囲でツバを付けちゃえばいいってことですね。
「まあ、言い方は汚いけど、そういうことかな。先に出願することが最大の自衛策、ってことだね」
これからの中国について

—でも、中国って結局は、他人のふんどしで相撲をとろうとしてばかりなんですかねえ。もう、世界の立派な大国だっていうのに。
「いや、その評価はちょっと酷すぎるような気がするね。中国での、この一連の商標トラブルは、ある種の過渡期的な現象とも言えるんじゃないかな」
—過渡期的…。
「うん。一昔前、“世界の工場”なんて呼ばれて、先進国の製品を生産するばかりだった中国は、21世紀を迎えて目まぐるしい経済成長を果たし、いまや堂々たる“世界の市場”へと変貌を遂げているね。中国の商標登録事情は、西欧諸国や日本の人たちの感覚からすると、目に余るというのはわからなくはないけれど、日本だって少し前までは、西洋の地名に関する商標がのほほんと登録されていた時代があったんだ。知財に対する認識が定着するのには、時間がかかるものだよ。と言っても、もちろん、中国の冒認出願を是としているわけでは、決してないんだけどね」
—なるほど〜、そう言われると、すうっと腑に落ちました。
「それはよかった」
—加藤さん、お忙しいところ、どうもありがとうございました。それでは、ぼくもここいらで失礼して。また次回まで、みなさん、ごきげんよう。
新米編集長・浅見杳太郎、頓首。